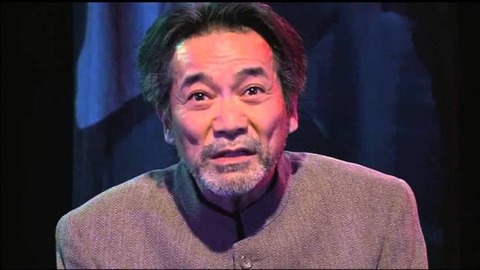Artist Maggie Lindemann

Album 『SUCKERPUNCH』

Tracklist
01. intro / welcome in
02. take me nowhere
03. she knows it
04. casualty of your dreams
05. self sabotage
06. phases
07. i'm so lonely with you
08. break me!
09. girl next door
10. we never even dated
11. novocaine
12. you're not special
13. hear me out
14. how could you do this to me?
15. cages

Album 『SUCKERPUNCH』

Tracklist
01. intro / welcome in
02. take me nowhere
03. she knows it
04. casualty of your dreams
05. self sabotage
06. phases
07. i'm so lonely with you
08. break me!
09. girl next door
10. we never even dated
11. novocaine
12. you're not special
13. hear me out
14. how could you do this to me?
15. cages
2016年に発表したシングルの“Pretty Girl”がバズった事でも知られる、約600万人のフォロワーを誇るインスタグラマー兼シンガーソングライターこと、マギー・リンデマンの1stアルバム『SUCKERPUNCH』の何がファッキンホットかって、過去にバズった“Pretty Girl”の毒にも薬にもならないインディポップみたいな曲調に反して、(その名残として)在りし日のアヴリル・ラヴィーン的なティーン向けのガールズポップ/パンクのキャッチーさを保持しつつも、それこそ00年代の洋楽ロックシーンにおけるゴシック系オルタナティブ・ヘヴィ代表のEvanescenceやFlyleafを連想させるハードロックを現代に蘇らせ、そしてエイミー・リーとFlyleafのレイシーとChvrchesのローレン・メイベリーを足して3で割ったような内省的な儚さと、いわゆるどこまでも堕ちていく系のロンリーな孤独を抱えたマギーのロリータボイスが激エモなヘヴィロックやってる件について。
決して、過去に流行った女性ボーカル物のロックの二番煎じではなく、その古き良き“00年代の洋楽ロック”と、BMTHのオリヴァー・サイクスが仕切ってる事でもお馴染みの20年代を象徴するアイコンがピックされたプレイリスト【misfits 2.0】の文脈が邂逅する、つまり在りし日の洋楽ロックの熱気とZ世代を司るハイパーポップ然としたヤニ臭いサイバーパンク精神を紡ぎ出す、それこそ次世代アーティストおよび次世代インスタグラマーを称するに相応しい、いま最もファッキンホットな存在が彼女なんですね。
アルバム後半においても、Evanescenceリスペクトな重厚感溢れる#9“girl next door”、アコースティックなシットリ系のバラードも聴かせるボーカリストとしてのポテンシャルを伺わせる#10“we never even dated”、オルタナティブな#11“novocaine”、MGKファミリーらしいアヴリル風ポップパンクの#12“you're not special”、本作のハイライトを飾る#7と共にどこまでも堕ちていきながら2秒でインスタフォロー不可避の#13“hear me out”、オーランドのエモ/ポスト・ハードコアバンドSleeping With Sirensのケリン・クインをフィーチャリングしたParamore風ポップパンクの#14“how could you do this to me?”、最後に改めて現代のアヴリルを印象付ける、曲調もMVのファッションも当時のアヴリルをオマージュした#15“cages”まで、確かにギターをはじめ音作りに対する不満はないと言ったら嘘になるけど、FlyleafのCoverを発表するくらいには00年代ヘヴィロックの影響下にある音楽性、同様に影響を受けているであろうBMTHのオリィが仕切ってる【misfits 2.0】に対する求愛行為に近いアプローチも含めて、アヴリル・ラヴィーンが洋楽のアイコンだった『あの頃』のノスタルジーと、時を経てマシンガン・ケリーをアイコンとするポップパンク・リバイバル(≒BMTH~Evanescenceの共演)、およびZ世代を象徴するハイパーポップの精神性を兼ね備えたハイブリッドな洋楽ロックは、体感2秒でマギーのインスタフォローすること請け合いのファッキンホットな魅力を放っている。
その手の“雰囲気”を醸し出すイントロSEに次ぐ#2“take me nowhere”からして、00年代にタイムスリップした気分にさせる、さながら現代のエイミー・リーとばかりに奈落の底までGoing Underしながら2秒でインスタフォローするレベルのダークなロックチューンで、一転して「現代のアヴリル」あるいは【アヴリルmeetチャーチズ】、さしずめ「女版マシンガン・ケリー」とばかりにポップパンク・リバイバルよろしくな#3“she knows it”、BMTHのジョーダン・フィッシュさながらのダイナミクス溢れるシンセやトラッピーなイマドキのアレンジを効かせた#4“casualty of your dreams”、再びEvanescenceやFlyleafの影響下にあるモダンなパワーバラードの#5“self sabotage”、オルタナティブな雰囲気を醸し出すPoppyヨロポッピーな#6“phases”、そして闇堕ちしたマギーの歌声と00年代オルタナ/ヘヴィロック然としたリフ回しからして、初期Evanescenceの伝説的な名盤『Fallen』を確信犯的にオマージュしてのける#7“i'm so lonely with you”は、耳にした瞬間から00年代のメインストリームの洋楽ロックリスナーなら「これごれぇ!」とガッツポしながら慟哭不可避だし、スクリレックスやプッシー・ライオット文脈のSiiickbrainをフィーチャリングした#8“break me!”においては、『amo』以降のBMTHリスペクトな客演パートの歌メロと「ウチら【misfits 2.0】入りしたいんや!チュパチュパ...」とナニをSucksするハードコアなアレンジまでもハイパーポップ然としており、そのヤニ臭い毒素とセクシャリティの解放を訴える反骨精神むき出しの主張はMVにも強く反映されている。
アルバム後半においても、Evanescenceリスペクトな重厚感溢れる#9“girl next door”、アコースティックなシットリ系のバラードも聴かせるボーカリストとしてのポテンシャルを伺わせる#10“we never even dated”、オルタナティブな#11“novocaine”、MGKファミリーらしいアヴリル風ポップパンクの#12“you're not special”、本作のハイライトを飾る#7と共にどこまでも堕ちていきながら2秒でインスタフォロー不可避の#13“hear me out”、オーランドのエモ/ポスト・ハードコアバンドSleeping With Sirensのケリン・クインをフィーチャリングしたParamore風ポップパンクの#14“how could you do this to me?”、最後に改めて現代のアヴリルを印象付ける、曲調もMVのファッションも当時のアヴリルをオマージュした#15“cages”まで、確かにギターをはじめ音作りに対する不満はないと言ったら嘘になるけど、FlyleafのCoverを発表するくらいには00年代ヘヴィロックの影響下にある音楽性、同様に影響を受けているであろうBMTHのオリィが仕切ってる【misfits 2.0】に対する求愛行為に近いアプローチも含めて、アヴリル・ラヴィーンが洋楽のアイコンだった『あの頃』のノスタルジーと、時を経てマシンガン・ケリーをアイコンとするポップパンク・リバイバル(≒BMTH~Evanescenceの共演)、およびZ世代を象徴するハイパーポップの精神性を兼ね備えたハイブリッドな洋楽ロックは、体感2秒でマギーのインスタフォローすること請け合いのファッキンホットな魅力を放っている。
【エッジランナーズのレベッカ】×【マギー・リンデマン】=【misfits 3.0】
個人的に、この手の次世代アーティスト兼インスタグラマーと聞いて想起するのは、他ならぬカナダのPoppyことモライア・ローズ・ペレイラやNova Twinsだったりするけど、このマギー・シンプソンはそのどちらにも属さない独自の路線を突き進んでいる。(一足先に合流したサラ・ボニトのように)将来的にBMTHのオリィとコラボして、晴れて【misfits 2.0】入りするかは予測不能だけど、念のため今から予言しときます→
「こーれ来年のサマソニで来日します」