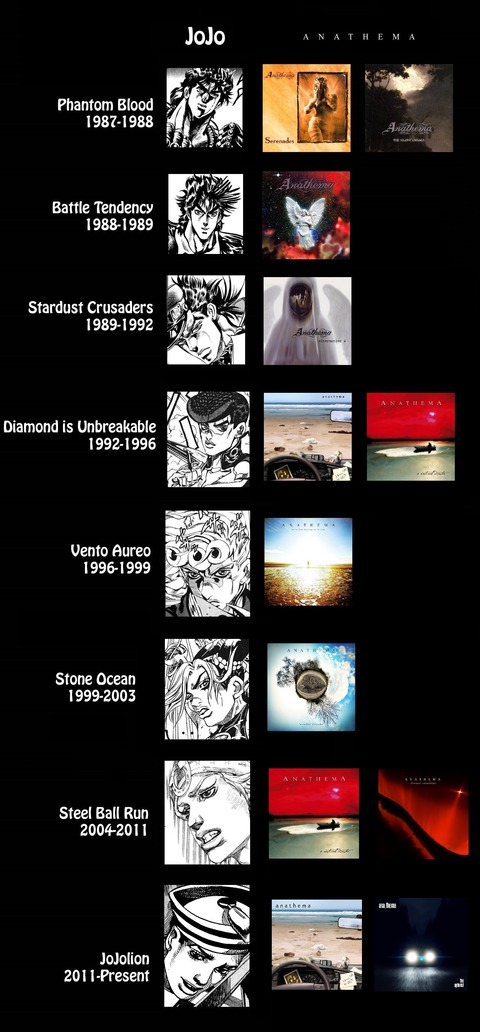Artist Susanne Sundfør

Album 『Music for People in Trouble』

Tracklist
世間が「平和の祭典」とされるオリンピックに熱狂する中、方や中東地域では今なお復讐の連鎖、報復の連鎖による紛争がやまない雨の如く後を絶たないでいる。この諸行無常の世界に救いの手を差し伸べるのは、やはり「音楽」なのかもしれない。いま一度、改めて「音楽の力」を再確認すべき時代がやってきたのかもしれない。このアルバムは、昨今より「繋がり」が求められる時代に、ノルウェイの歌姫スザンヌ・サンドフォーは北朝鮮とアメリカ、ネパールやブラジル、そしてアマゾンのジャングルに至る大陸を横断する旅路の中で、いま世界中で対立し合う国同士、いま世界中でいがみ合う人々の想いを一つ一つ紡ぎ出し、そしてバラバラに分断された国や地域を再び一つの世界に統一される事を祈るような、そんな「平和の象徴」=シンボルを謳った「和平の音楽」である。

Album 『Music for People in Trouble』

Tracklist
1. Mantra
2. Reincarnation
3. Good Luck Bad Luck
4. The Sound Of War
5. Music For People In Trouble
6. Bedtime Story
7. Undercover
8. No One Believes In Love Anymore
9. The Golden Age
10. Mountaineers
世間が「平和の祭典」とされるオリンピックに熱狂する中、方や中東地域では今なお復讐の連鎖、報復の連鎖による紛争がやまない雨の如く後を絶たないでいる。この諸行無常の世界に救いの手を差し伸べるのは、やはり「音楽」なのかもしれない。いま一度、改めて「音楽の力」を再確認すべき時代がやってきたのかもしれない。このアルバムは、昨今より「繋がり」が求められる時代に、ノルウェイの歌姫スザンヌ・サンドフォーは北朝鮮とアメリカ、ネパールやブラジル、そしてアマゾンのジャングルに至る大陸を横断する旅路の中で、いま世界中で対立し合う国同士、いま世界中でいがみ合う人々の想いを一つ一つ紡ぎ出し、そしてバラバラに分断された国や地域を再び一つの世界に統一される事を祈るような、そんな「平和の象徴」=シンボルを謳った「和平の音楽」である。
前作の5thアルバム『Ten Love Songs』は、それはまるで荻野目洋子の”ダンシング・ヒーロー”のような、あるいは「北欧の西野カナ」のような、もしくはCHVRCHESやChelsea Wolfe、同郷の妹分であるAURORAに対する回答であるかのような、シンセをはじめイマドキの電子音楽をフィーチャーした、ある種の80年代の歌謡シンセ・ポップに振り切った作風で、そして何よりも”Kamikaze”=「カミカズイ~」的な意味でも俺の中で話題を呼んだ。そんな彼女を一躍「ポップスター」に押し上げる大きなキッカケとなった、トム・クルーズ主演のSF映画『オブリビオン』の主題歌に起用されたM83とのコラボ(2013年)から同郷のエレクトロユニットRöyksoppとの再コラボ(2016年)に至る一連の流れから一転して、通算6作目となる今作の『Music for People in Trouble』では、彼女の原点である「シンガーソングライター」としてNEXT_の次元に進んだことを宣言するような、決して前作のような「ポップスター」さながらのキラキラした派手さはないが、シンプルにスザンヌの芯の通った歌声が胸に染み渡る大人のフォークソングを聴かせる。
2017年内の話でも、LAのPhoebe BridgersやUKのMarika Hackmanを筆頭に、いわゆる昨今のフォーク・ミュージック・リバイバル的な潮流に沿った案件でもあって、アコースティック・ギターを中心にグランドピアノやペダルスティール、フルートやクラリネット、更にはサックス、時にはスポークン・ワードを駆使しながら、その清らかな世界観を構築していく。ゲストにはレーベルのベラ・ユニオン繋がりでもあり、スザンヌが敬愛してやまないジョン・グラントが10曲目に参加し、マスタリングにはThe War On Drugsや岡田拓郎くんの『ノスタルジア』でもお馴染みのグレッグ・カルビという、その手のインディ系フォーク・ミュージックの分野に長けた文字通りプロフェッショナルなエンジニアを迎えている所にも、今作のただならぬ「こだわり」を伺わせる。
スザンヌ自身が「今の時代って物事が次から次へとすごいスピードで変化してて、時にそれは暴力的で圧倒される。たくさんの人が不安を抱えていると思うの。わたしはそういった感情をこの作品を通して表現したかったの」と語るように、テクノロジーの進化、インターネット時代の到来、そしてSNS疲れなどの一種の現代病から解放するような、そして行き過ぎた資本主義がデッドラインを超えて世界中に蔓延する格差社会、それらを一度「無」に帰すような、人間が持つ本質的な部分に訴えかけるような、そんな現代人の荒んだ心に安らぎと平穏、そして調和を与えてくれる。例えるなら、これはまさに「楽園の音楽」だ。
スザンヌが世界中の国々を訪れる中で彼女が辿り着いた一つの答えこそ、かのニーチェが提唱した「ニヒリズム」の思想だった。その虚無主義的な思想を音楽を通じて表現するにあたって、スザンヌが導き出したのがより身近により自然体で奏でる、まるでその場に寄り添うような自然の音楽、よりオーガニックでよりアナログかつアンプラグドな、それはまるで「アンチ・テクノロジー」の音楽、そしてそれは世界中の人々の耳に届く「自由の音楽」だった。この音楽には、自分の体で、自分の目で世界を確かめた人間だからこそ成せる、ぐうの音も出ない説得力に溢れている。これこそ「今の音」だ。
ペダルスティールを駆使した#1”Mantra”と#2”Reincarnation”の冒頭からして、The War On Drugsをはじめとしたその手のピッチフォーク界隈への迎合を図ったような曲で、そんな中でも、今作の目玉となる#4”The Sound Of War”から#5”Music For People In Trouble”の流れは圧巻の一言だ。そこは争いのない小鳥のさえずりがこだまする美しく広大な地球を舞台にアコギ一本で語り弾く女神=シンボルという、もはや不気味なくらい平和な光景から一転、すると前触れもなく「ソレ」はやってきた。その曲調からして、「ソレ」はまるで平穏な日常に忍び寄る恐怖、それこそ”戦争の足音”すなわち「散歩する侵略者」の足音が聞こえてくるような、その「音(Sound)」こそ人類が最も恐るるべき「恐怖(Fear)の音」である。
前作では”Kamikaze”という曲でスザンヌなりの”Love”を描き出していたが、この”The Sound Of War”では自身の実体験とも呼べるより”リアル”な恐怖(Fear)を与えることで、より強い”Love”、そして”Peace”を人々の潜在意識に植え付けている。同郷の「繋がり」で言うと、ノルウェイの森のクマさんことUlverが地元のオーケストラとコラボした『Messe I.X - VI.X』、あるいは坂本龍一の『async』みたいなアンビエント・ポップ/スポークン・ワード的なスピリチュアルな世界観、もしくはエンヤやJulianna Barwick的なニューエイジ回帰というか、デビュー10周年にして彼女は何を悟ったのか、過去最高にスザンヌのパーソナルな部分と”Love&Peace”なリベラリズムが「音(Sound)」に込められている。ちょっと面白いのは、同じく2017年にリリースされたUlverの新作『The Assassination of Julius Caesar』がスザンヌの前作『Ten Love Songs』っぽいシンセ・ポップな作風で、逆にスザンヌの新作『Music for People in Trouble』がUlverの前作『Messe I.X - VI.X』っぽい作風になってるところで、これはそろそろコラボあるんじゃねー的な淡い期待。とにかく、色々な意味で今作はHostessから国内盤が出てもおかしくない内容。
4thアルバムの『The Silicone Veil』以前の「天上の歌声」と称すべき彼女の超絶歌唱が堪能できる#7”Undercover”は今作のハイライトで、そしてよりエンヤっぽさを醸し出す#9”The Golden Age”、そしてジョン・グラントとスザンヌのデュエット曲となるラストの#10”Mountaineers”まで、とにかくこれまで以上にミニマムなスタイルでありながらも、その「音(Sound)」が奏でる”Love”に、過去最大級のスケールに只々圧倒されると同時に、でも不思議と身を委ねてしまう心地よい癒やしの空間でもある。作品の完成度は過去作と比べても全く引けを取らないし、少なくとも前作よりはスルメっぽいアルバムで、噛めば噛むほど聴けば聴くほど味が出てくる感じ。改めてみても、これはちょっと凄い。彼女、もうエンヤとジュリアナ・バーウィックと同じ領域にいる。


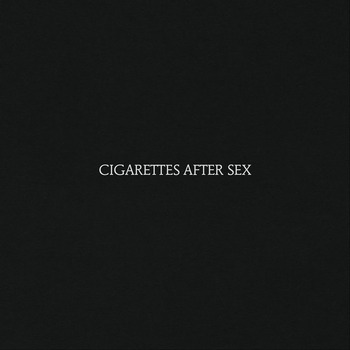
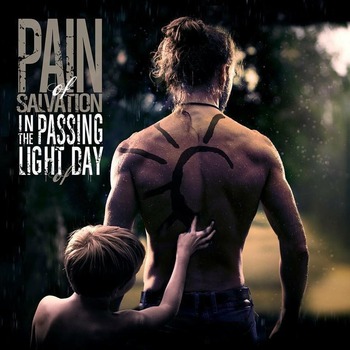





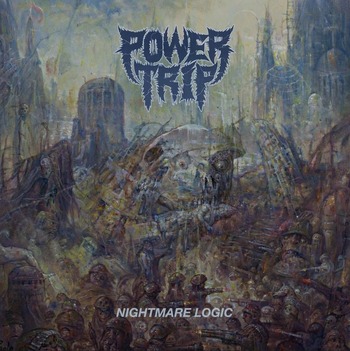



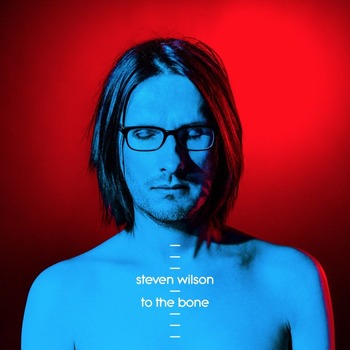









 「こんばんは、稲川VR淳二です。」
「こんばんは、稲川VR淳二です。」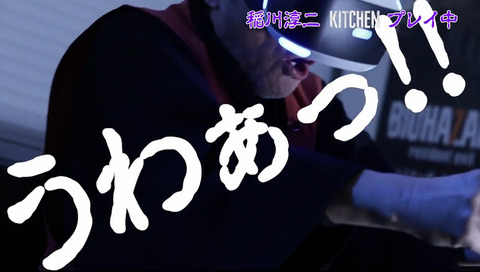




 「ガチャ」
「ガチャ」 「へいっ!いらっしゃい!何にする?」
「へいっ!いらっしゃい!何にする?」 「よぉ~、モ~元気かぁ~?」
「よぉ~、モ~元気かぁ~?」 「まっ、ここには原発とダフビールとドーナツしかないけど、楽しんでってくれ」
「まっ、ここには原発とダフビールとドーナツしかないけど、楽しんでってくれ」 「D'oh!!でも別にいっか」
「D'oh!!でも別にいっか」 「じゃね~」
「じゃね~」