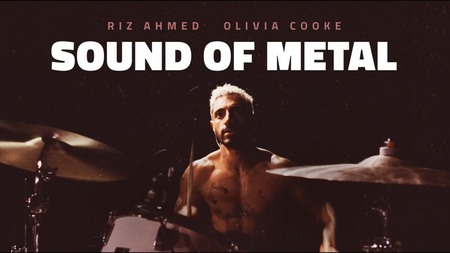
アマゾンプライムビデオで配信中のリズ・アーメッド主演の映画『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』を5回観ての感想をば。
初期のCode Orangeを彷彿とさせる、グランジ風のアンダーグラウンド・メタル/ハードコアバンド=BLACKGAMMON(ブラックギャモン)のドラマーであるルーベン(リズ・アーメッド)と、その恋人でありバンドのギター兼ボーカルを担当しているルー(愛称ルイーズ)(オリヴィア・クック)は、自前のトレーラーハウスを運転しながら各地のライブハウスをどさ回りするバンドマンだ。そんなある日、ドラマーであるルーベンが徐々に聴力を失う難聴を患うも、教会が支援するとある治療施設の聴覚障害者のコミュニティに歓迎され、そこでルーベンは様々な大人や子供と出会う。初めは馴染めずにいたルーベンは、手話を身につけると徐々に他の盲ろう者とも打ち解けていく。しかし、一方でバンドマンとしての夢を諦めきれない自分と現実の狭間で葛藤しながら、将来の人生について大きな選択を迫られる一人のバンドマンをめぐる物語。
恋人であるルーとは、いわゆる普通の恋人関係というよりは、先の見えない不安という心の隙間を埋め合うように、何かしらの依存症を持つ者同士お互いに依存し合う関係性だ。このような依存関係って現実世界でも別に珍しくもなくて、今回の例とは少し勝手が違うけど、例えるなら売れないバンドマンとそれに貢ぐメンヘラ女はその最たる例の一つだ。何を隠そう、この映画はその「依存症」が一つのキーワードとなっていて、ルーベンはルーと出会う4年前までヘロイン中毒者だった過去を持ち、片や恋人のルーはルーで左腕に年季の入ったリストカットの傷跡が夥しくあり、今もリスカの後遺症なのか腕を指で引っ掻くクセがある。そんな自傷行為という名の依存症を患っている二人の男女が織りなす映画で、ルーベンとルイーズ(呼び名はルー)で少し名前が被ってるのも、依存症を持つ者同士依存し合う同類であるという一種のメタファーなのかもしれない。
コミュニティの長であるジョーが入所前のルーベンに放った言葉「耳を治すのではなく心を治す」。これこそが本作における最大のパンチラインで、簡単に言えば「人生の不幸」とは耳が聞こえないことではなく、「心の平穏」が存在しないことであるという教え。ルーベンはコミュニティで老若男女の様々なろう者と交流を深めていく中で、人生における「真の幸福」に気づきかけてきた矢先、未だ彼の中に眠るバンドマンとしての想いがそれに抗う。
映画の中盤を構成する聴覚障害者施設パートは、序盤のライブハウス内の爆音とは真逆のBGMらしいBGMがほとんどない(そこにあるのは虫や小鳥のさえずりなどの環境音楽=アンビエント音楽だけ)、つまりメタル/ハードコアという音楽ジャンルで最も耳の環境に悪いラウドな環境から、一転して盲ろう者だけの静かな自然に取り囲まれた真逆の環境に身を置く事となる。ここで、「なぜ本作の主役がメタルバンドのドラマーなのか?」という皆が気になっているであろう疑問の答えを想像するに、恐らく対象が「無音」あるいは「環境音」から最も遠い存在だから説w いや、笑い話でもなんでもなくて、映画の演出的な部分でもライブハウスでの粗暴な怒りに満ち溢れた感情的な爆音と、人里離れた緑豊かな森林に囲まれたコミュニティで流れる無音あるいは環境音、そのギャップを効かせた「音響」の演出は監督が意図したものだと思う。だから別に監督がメタルに対して悪いイメージや偏見があるわけではないと思う(謎のフォロー)。
さっきまでの環境音パートが嘘のように、それこそ「嵐の前の静けさ」とばかりに、不穏な未来を暗示するかのような「ゴゴゴゴ」という轟音を放つ黒い雨雲から場面は終盤へと切り替わり、そして恐怖のノイズ地獄が幕を開ける。ルーベンは決意し、自前のトレーラーハウスと音楽機材を全て売り払い、高額な手術でインプラントを埋め込んで聴力を取り戻すも、所詮は「脳を錯覚させて聞こえるようにしている」だけの代物で、やはり「失われた聴力は二度と元に戻らない」と言われているように、彼の耳は完全な状態には戻らなかった。
それ以降のシーンはホラー映画にも似た恐怖を覚えた。その後、ルーベンはフランスの実家に帰っているルーに再会すべくフランスへと渡る。彼女と再会すると、そこには眉毛を銀色に染め上げ、ステージ上で「ホールこそ私のゴールなの そこにいて欲しい 暴いて欲しい 意外とウブなあんた あたしが食べてあげる」というような謎の歌詞を怒りと共に咆哮していたバンドマンとしてのルーの面影はなく、欧米人らしく賑やかなパーティに参加する一般的な普通のフランス人女性としての日々を過ごしていた。そんな別人となったルーを一眼見ると、ルーベンは真っ先に彼女の左腕に引っ掻き傷の跡がないことに気づく。パーティではフランス映画界のレジェンド=マチュー・アマルリック演じるルーの父親のピアノの伴奏に合わせて、娘のルーがライブハウスで放ってい自殺的で暴力的で悲劇的な咆哮とは真逆の美しい歌声を母語であるフランス語で披露する。このシーンは本作最高の名ホラーシーンでもある。
パーティが終わり、それこそ二人してトレーラーハウス内のベッドで寝ていた時と同じように、ルーの部屋のヘッドで恋人同士らしくイチャイチャムードに発展するや否や、またしてもルーベンはルーが再び左腕を引っ掻くクセ=依存症が再発したことに気づく(このベッドシーンでルーが水を飲む場面は、序盤の演奏シーンの歌詞の伏線回収でもある)。そこでようやくルーベンは、極度の不安やストレスから発作のように引き起こされる腕を引っ掻くクセ=依存症の原因は自分にあると理解する。4年前にルーと出会ってドラッグ依存から抜け出せたルーベンとは違い、ルーはルーベンがいることで依存症がぶり返す精神的不安の状態、それを誘発するトリガー的な存在でしかない哀しい現実を知ってしまう。ルーベンとルー(ルイーズ)、皮肉にも互いに助け合い依存しあってきた恋人同士の二人が別れて初めて依存症からの真の解放を得る事となる。
このベッドシーンは、精神的にも経済的にも不安定で継続的なストレス状態に晒されていたバンド時代からの解放を示唆し、バンド時代とは真逆のフランスの実家という安定した環境がルーの精神に安堵感を与え、バンド時代には得られなかった「心の平穏」を取り戻した場面。翌朝、全てを察したルーベンは別れの挨拶もなしにルーの実家を抜け出し、あてもなくフランスの街を彷徨い、しばらくしてからフランスの平凡な日常と街並みが見渡せるベンチに腰掛ける。しかし、今のルーベンの耳には、街にこだまする人々の日常会話も、教会の荘厳な鐘の音も、親子の美しい歌声も、自然が奏でる環境音すらも全てがノイズ=騒音にしか聞こえない恐怖。ルーベンは何を思ったのか、その場でインプラントを取り外して完全なる「無音」状態に身を置く。この「完全なる無音」という「真の静寂」に彼は何を感じ、そして何を聞いたのだろうか?それは彼だけにしかわからない事なのかもしれない。しかし、彼はその瞬間に初めて「耳を治すのではなく、心を治す」と言ったジョーの言葉を理解したに違いない。そう、今まさに自分が置かれている「無」の状況こそジョーの言った「心の平穏」であると。
なんだろう、例えるなら仏教における「諸行無常の響きあり」じゃないけど、彼の耳には教会の大きな鐘の音も聞こえない「無音」のはずなのに、今の彼は「心の平穏」の中でしっかりと鐘の音が響き渡っているに違いないと。ルーベンにとって「無音」こそが「心の平穏」だと気づくこのラストシーンは見事としか言いようがない。美しい、ただただ美しい「無音」。それこそ日本の禅の精神じゃないけど、それに限りなく近い「無(音)」にあることが人間の真理であり幸福であるという教え。これ何が凄いって、最終的に神の存在を問うレベルの領域に物語が収束していく事で、デフォで歌詞に「Anti Christ」入ってるような(ただの偏見)、バックグラウンドや思想としてアンチ・クライストあるいは無神論者および無宗教である“メタラー”のルーベンがたどり着いた「真の幸福」、その答えが仏教的なオチだったのはちょっとというか相当な皮肉。でもそれが、それこそが、この映画の主人公になぜ“メタラー”が選ばれたのか?その本当の理由なんだって。この映画、いろいろな意味でメタラーじゃなきゃ成立しない映画なんですね。
本作は「対比」が一つのメタ的な演出として、また音楽的な構成を築き上げている。まず序盤はライブハウスで怒りの感情に満ち溢れたメタル/ハードコア、中盤は自然に囲まれた環境音楽=アンビエント、終盤のインプラント手術以降はノイズ、そしてラストシーンは「無音」という、音楽的なメタ構成も意図的に狙ってやってるんじゃないかと思うぐらい、各パートを司る「音の変化」もルーベンの感情の変化と共鳴している。
この映画、ありがちな「耳を大事にしよう」みたいな啓発映画なんかじゃなくて、もちろん健常者に対する「耳を大事に」的な啓発目的もなくないだろうけど、むしろ聴覚障害者の視点から盲ろう者側から見える世界、ろう者側の理念であったり、ろう者の幸福についてだったり、耳が聞こえる聞こえないの話じゃなくて、身体的なハンデよりも心の問題などの内面的な部分を描いている。
人間、誰しもが何かに「依存」して生きている。それは耳が聞こえる人間にも、耳が聞こえない人間にも等しく平等に存在する。障害を扱っている映画だから健常者の自分には関係ない他人事の話なんかじゃ決してなくて、耳が聞こえる健常者にも、耳が聞こえない盲ろう者にも共感する部分がそれぞれ平等にある、そんな真のバリアフリー映画だと思った。このように障害を擬似体験させる似たような映画だと、最近では視覚障害を扱ったNetflixの『バードボックス』を思い出した。哲学的?なオチもそれっぽいっちゃそれっぽいし。
人間、誰しもが何かに「依存」して生きている。それは耳が聞こえる人間にも、耳が聞こえない人間にも等しく平等に存在する。障害を扱っている映画だから健常者の自分には関係ない他人事の話なんかじゃ決してなくて、耳が聞こえる健常者にも、耳が聞こえない盲ろう者にも共感する部分がそれぞれ平等にある、そんな真のバリアフリー映画だと思った。このように障害を擬似体験させる似たような映画だと、最近では視覚障害を扱ったNetflixの『バードボックス』を思い出した。哲学的?なオチもそれっぽいっちゃそれっぽいし。
ルーベンが日本の伝説的ハードコアバンド=GISMのTシャツを着ている場面を筆頭に、数あるメタル雑誌の中から選ばれたのがエクストリーム系のDECIBEL MAGAZINEってのが地味にわかってる感凄いし、トレーラーハウスの内装に貼り付けてあるフライヤーにPINKU JISATSU(ピンク自殺)やVIOLENT PACHINKOという架空のヴィジュアル系バンドの名前が載ってる、と思ったらその2組のバンドは本当に実在する(前者は)スペインのヴィジュアル系らしくて(ちなみにルーの母親の死因は自殺)、とにかく雑誌の表紙やインタビューページの切り抜きを含めて、メタル/ヴィジュアル系/ハードコアに関するプロップ(小道具)や資料関係がメタラー視点から見ても相当コアでマニアックな映画である事がわかる。
後半、舞台がフランスに移るってのもあるし、フランス映画界のレジェンド俳優や実際に盲ろう者の役者を起用している点、そしてドキュメンタリータッチというわけではないけど、いわゆるハリウッド映画のそれとは違うカメラワークもフランス映画というか欧州映画の匂いが強い。監督は映画『プレイス・ビヨンド・ザ・パインズ』の脚本を担当したダリウス・マーダーとのことで(そういえばこの映画のゴズリングはメタリカTシャツ着てた気がする)(むしろ監督メタラー説)、(このご時世な事もあって全然観てないけど)今年の年間BEST映画1位間違いなしの一本だし、メタラーでもメタラーじゃなくても全てのミュージシャンに勧めたい映画でもあるし、同時に映画監督は元より音響監督こそ見るべき音響映画でもあり、それこそ某佐村河内もアニメ『聲の形』のヒロインこそ観るべき、いやもう全人類が観るべき映画です。初めて「アマゾンスタジオすげぇ・・・」ってなったくらいには名作なんで。確かに、聴力も元に戻らなければ、バンドマンとしての未来も閉ざされちゃったから絶望っちゃ絶望だけど、ルーベンは最後の最後で「心の平穏」を見つけ出せたから普通にハッピーエンドだと思う。
改めて、耳を大事にしようという至極当たり前なことでもあっても、いざライブでテンション上がっちゃうと自分の耳の健康を蔑ろにしがちだから自戒の意味を込めて、この状況下でライブに足を運べない時だからこそ、いま一度再確認すべきタイミングなんじゃないかって。ルーベンと一緒に、この映画のラストシーンのエンドロールで初めてジョーの言葉、その重みを痛感すること請け合い。
しかし、主演のリズはジェイク・ギレンホール主演の映画『ナイトクローラー』で初めて知って、HBOドラマ『ナイト・オブ・キリング』でも難しい役柄を演じていたけど、今回も手話やドラムの練習を積んで役に挑んでいて、改めて良い役者だなぁと再認。でもそれ以上に『レディ・プレイヤー1』のオリヴィア・クックの方が「モデルはコード・オレンジのレバ・マイヤーズさんですか?」とツッコミ不可避の役作りがハンパない。流石にあの眉毛はやりすぎだけどw
難聴のリスクはステージに立つミュージシャンだけの問題ではなく、ライブハウスに足を運ぶリスナー側の問題でもある。よくロックやメタルのライブに行く人なら経験あると思う。ライブ終演後に「ピー」という耳鳴りがする経験が。というのも、これを書いている僕自身、Deafheavenの観客が10人くらいしかいなかったいわゆる「伝説の名古屋公演」の際に、人がいないから必然的にスピーカーの前で観る事になって、しかも耳栓を着用してなかったからそのライブ後は二週間ぐらい耳鳴りが治らなかった経験者だ。そういうリアルにヤバい状況に陥った人間がこの映画を観ると正直「シャレにならない、もう笑えない」、そんな話なんですね。幸い、というか運よく耳鳴りの症状は完治したんだけど、ヘタしたらそのまま難聴コースになって映画のルーベンと同じ道を進む可能性があったと想像しただけで恐怖しかない。もちろん、そのDeafhevanの伝説の名古屋公演以降(2回目の来日公演も含む)は必ずライブ用耳栓を着用してライブに行くようにしてます(でも去年のBMTHのライブではテンション上がってしなかった)(←こういうのがダメ)。
そんなDeafheavenの10周年デビューを記念するスタジオライブアルバム『10 Years Gone』は、メンバーは元よりスピーカーからエグいぐらいのギターノイズを(ルーベンもドン引きするぐらい)超至近距離から鼓膜ダイレクトで浴び続けた伝説の名古屋公演の軽いトラウマとともに、今やメタルシーンを代表するバンドにまで成り上がったバンドへの感慨深い想いがふつふつと浮かび上がる。相変わらずバチグソ丁寧な演奏してんなって思うし、何よりも選曲が最高過ぎる。まず一曲目が個人的に5本指に入るぐらい好きな曲であるシングル曲の“From the Kettle Onto the Coil”とか「こいつらわかってんな感」しかないし、いわゆる「指DEMO」時代の“Daedalus”も貴重過ぎるし、1stアルバムからは“Language Games”、3rdアルバムからはキザミとケリー・マッコイの慟哭のギターが映える“Baby Blue”、ラストはDeafheavenを司る2ndアルバムからバンド史上最高の名曲“Dream House”という、全8曲なのにどれもバンドを語る上で欠かせないし外せない完璧な選曲となっている。そんな最高のライブアルバムを聴いていると、久々にライブが観たくなってくるのはメタラーの性。
話を戻して、映画の中でジョーはルーベンに「書くこと」を勧める。アルコール依存症であるジョーは「書くこと」で「心の平穏」を取り戻していると。そのシーンでふと思った、自分にとっての「心の平穏」もジョーと同じ「書くこと」なのかもしれないと。今まさにこうやって音楽を聴きながら何かについて「書くこと」こそ「心の平穏」、あるいはそれに限りなく近い「無(音)」状態に繋がっているんじゃないかって。






