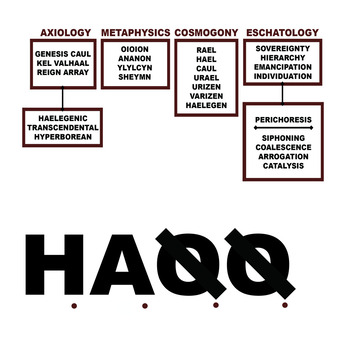Artist Tomb Mold

Album 『Planetary Clairvoyance』

Tracklist

Album 『Planetary Clairvoyance』

Tracklist
01. Beg For Life
02. Planetary Clairvoyance (They Grow Inside Pt 2)
03. Phosphorene Ultimate
04. Infinite Resurrection
05. Accelerative Phenomenae
06. Cerulean Salvation
07. Heat Death
10年代最後の年に“10年代最高のデスメタル”と呼ぶに相応しい名盤を発表したデンバー出身のBlood Incantation。このTomb Moldの3rdアルバム『Planetary Clairvoyance』は、それこそBlood Incantationの『Hidden History of the Human Race』に対する隣国カナダからの回答と言わんばかりの、それこそ新世代デスメタル女子こと環境保護活動家グレタ・トゥーンベリと広瀬すずがトゥース!ばりのデスポーズを決めながらデスボイスで「直腸陥没!」と咆哮しそうなデスメタルで、そのプログレッシブはプログレッシブでも(Protest the HeroやCryptopsyを輩出した)カナダ産らしい俄然テクデス寄りのサウンドとSFライクな世界観は、否応にもBlood Incantationと共鳴するデスメタルと言える。
しかし実際は今作を聴けば聴くほどBlood Incantationとの違いが顕著に感じられる。その最たる違いが現れるのは今作のリード曲となる表題曲の#2“Planetary Clairvoyance”で、テクデス然としたアグレッシヴな曲調で進むと、一旦曲が途切れたと思ったら急にイマドキのグルーヴ・メタルみたいなリフをブッ込んできてド肝抜かれた。なんだろう、楽器の音作りやサウンド・プロダクションの面でも90年代当時の空気感を内包した伝統的なデスメタルをリスペクトしていたBlood Incantationに対して、このTomb Moldは90年代のアンダーグラウンド・メタルというよりは2000年以降の比較的現代的なメタルの音像というか音作りを特徴としていて、それこそGojiraやSylosisにも精通するポスト・スラッシュ風のタイトなキザミを中心に、それと同時にDevilDriverにも通じるエクストリーム系の存外モダンでグルーヴィなリフ回しをもって、テクデスらしくファストとスローの緩急を効かせた曲構成と“イマドキのヘヴィさ”でゴリ押してくる。
この『惑星の千里眼』というタイトルといい、このデスメタル然とした読めないバンドロゴといい、そしてトドメは映画『エイリアン』にインスパイアされたようなアートワークといい、正直もっとSFなファンタジー要素を強く押し出してくると思いきや、それら諸々が醸し出すイメージとは裏腹に、実際に聴くと想像した以上にイマドキのデスメタルやってて驚いたというか、逆にそのギャップにやられた。それこそBlood Incantationは70年代のプログレッシブ・ロックにも精通する、一聴してわかる“プログレッシブさ”を取り込んだ“プログレッシブ・デスメタル”だったけど、このTomb Moldはもっとオーソドックスなヘヴィ・メタル寄りの、プログレッシヴ(な)デスメタルというよりかはテクデス然としたキレ重視のアグレッシブなスタイル。このそこはかとないモダンさをどう受け取るか、どう評価するかは聴き手次第といったところ。少なくとも、デスメタルならではの硫酸ドロドロなんでもデロデロ感はBIの方に軍配が上がる。なんだろう、適当なこと言っちゃうと、何か大手メタルレーベルのニュークリア・ブラストにいてもおかしくない感じw
そのステレオタイプのイメージが覆されて少し動揺しているうちに、ふと気づくと遠く彼方の宇宙空間にほっぽり出され、未知なる惑星=スーパーアースを彷徨うような、それこそBlood Incantationの『Hidden History of the Human Race』の世界線と同じルートに入ったかのような錯覚を憶えるぐらいSF然とした宇宙空間系デスメタル・インストの#3“Phosphorene Ultimate”、タイトでヘヴィなキザミで構成された#5“Accelerative Phenomenae”は今作のハイライトで、ラストを飾る#7“Heat Death”では流麗なソロワークを披露すると、最後のSEでは無数の繭から新種のエイリアン誕生という絶望的な光景を目の当たりにする(まるで気分はシガニー・ウィーバー)。
ただでさえ完成度の高い今作を優に超えてくるBlood Incantationの名盤『Hidden History of the Human Race』のズバ抜けた凄みを再確認しつつも、今作は今作でタイトでヘヴィで硬派なデスメタルの良作として、気鋭のデスメタル女子に対抗する2019年の二大デスメタルとしてオヌヌメしたい一枚デス!